40. バイポーラ・トランジスタの基本動作
バイポーラ・トランジスタ(Bipolar Transistor)は、半導体のpn接合を利用して実現したトランジスタの一種。接合型トランジスタとも呼ばれています。pnpとnpnという2つの接合構造があり、それぞれの接合構造で電流の流れる向きが逆になります。3端子構造で、それぞれの名称はエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)です。電流増幅やスイッチングなどの役割で利用されています。 バイポーラ・トランジスタの名前の由来は、動作にかかわるキャリアが電子と正孔の2種類あることから、バイ(2の意味)という呼称が使われています。ポーラは極の意味です。一方、電界効果型トランジスタ(FET: Field EffectTransistor)は、動作にかかわるキャリアが電子、もしくは正孔のみの1種類であるため、ユニ(1の意味)とポーラをつなげた呼称が使われています。最初に発明されたトランジスタがバイポーラ・トランジスタだったため、現在でも単にトランジスタと言った場合は、バイポーラ・トランジスタを指すことが多いようです。
特長
特長の1つとして、小さなベース電流に対して、その数十~数百倍相当にコレクタ電流が流れることが挙げられます。この特長を利用して、増幅機能を実現します。コレクタ電流は、コレクタ電圧が変動してもほぼ一定に保たれます(定電流特性)。ベース-エミッタ間はダイオードと同じ構造であるため、ベース電流を流すには、ベース電圧をエミッタ電圧に比べて、0.6~0.7V高く保たなければなりません(npn型の場合)。この電位差を利用して、スイッチング機能を実現します。一般に、電界効果トランジスタ(FET)と比べると、増幅率は高くなります。しかし、すべて電流モードで動作するため、全体として動作時の消費電力が大きくなってしまいます。大電力を扱う際には、電圧モードで動作する電界効果型デバイス(真空管やFET)に比べる不利になります。このため微小信号を増幅する際は、トランジスタを動作させるに必要な電流が得られなければ実現できないことになります。スイッチング素子として利用する際には、ダイオード接合に電流を流す構造に特有の少数キャリア蓄積効果のため、本質的に動作速度に限界がある点に注意が必要です。しかし、スイッチのオン/オフ制御信号として電流さえ流せば、電圧は接合部の飽和電圧(一般的なバイポーラ・トランジスタの場合で0.6~0.7V)しか必要ないため、電圧供給に制約がある用途では使いやすいと言えます。
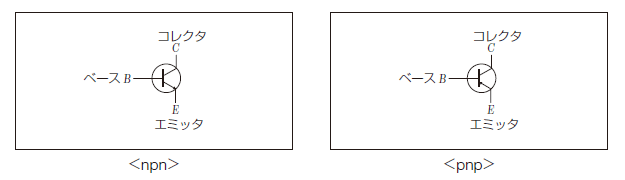
種類
前述のように、3つの端子はそれぞれエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)と呼ばれています。pnp構造とnpn構造のいずれも中央の端子がベースです。エミッタ、ベース、コレクタの端子は、真空管のカソード、グリッド、プレートの端子に、電界効果トランジスタ(FET)のソース、ゲート、ドレインに対応しています。npnトランジスタはn型、p型、n型の順番で半導体を積層したもので、pnpトランジスタはp型、n型、p型の順番で半導体を積層したものです。いずれも表記上は対称形ですが、実際のトランジスタでは、エミッタ側の半導体の不純物濃度を高めなければ正常な動作を実現できません。
主な最大定格
|
最大コレクタ・ エミッタ間電圧 |
|
ベースを開放の状態にした場合に、エミッタとコレクタの間に印加することが可能な最大の電圧値。これを超える電圧を印加すると、接合部でなだれ降伏が発生し、破壊されてしまう |
|---|---|---|
|
最大コレクタ・ ベース間電圧 |
|
コレクタとベースの間に印加できる最大の電圧値 |
|
最大エミッタ・ ベース間電圧 |
|
エミッタとベースの間に印加できる最大の電圧値 |
| 最大コレクタ電流 |
|
コレクタに連続的に流すことができる最大の電流値。もしくは実用に耐え得る増幅率が得られる最大のコレクタ電流値 |
| 最大ベース電流 |
|
ベースからエミッタに向かって流すことができる最大の電流値 |
| 最大コレクタ損失 |
|
連続して消費することができる最大のコレクタ電力損失 |
主な電気的特性 遮断周波数
| 直流電流増幅率 |
|
エミッタ接地増幅回路における、ベース電流とコレクタ電流の比 |
|---|---|---|
|
|
電流増幅率が1になる周波数。トランジション周波数とも呼びます |
