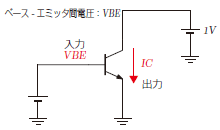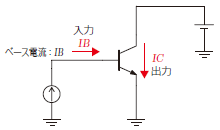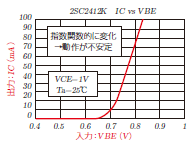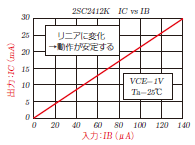42. 抵抗内蔵トランジスタの基本
抵抗内蔵トランジスタは、バイポーラ・トランジスタに抵抗を
追加したもので、デジタル・トランジスタとも呼ばれます。
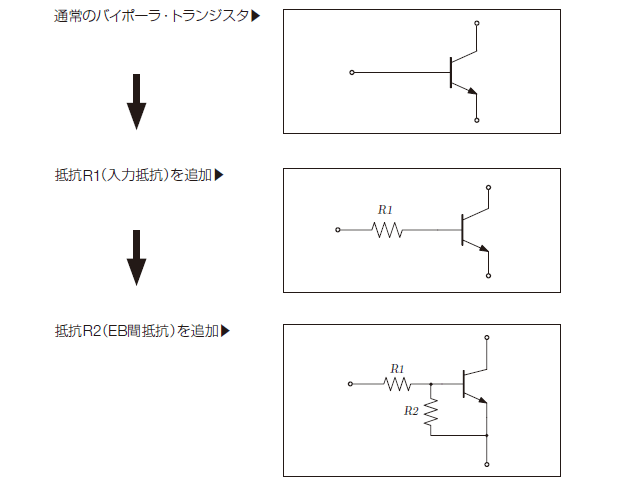
(1)抵抗R1 について
抵抗R1の役割:入力電圧を電流に変換してトランジスタの動作を安定させます。 バイポーラ・トランジスタは、入力(ベース端子)にIC などの電圧出力を直付けして電圧制御で動作させると、動作が不安定になります。 IC とベース端子の間に抵抗(入力抵抗)を入れて電流制御として動作させることで動作を安定させることができます。 これは、出力電流は入力電圧に対して指数関数的に変化しますが、入力電流に対してはリニアに変化するためです。 この入力抵抗を内蔵したのが、抵抗内蔵トランジスタの抵抗R1です。
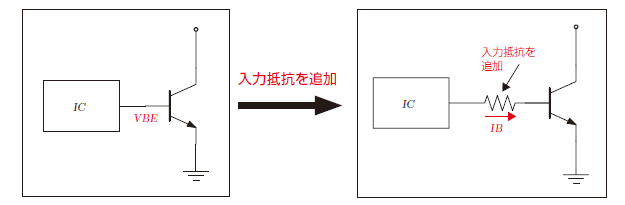
動作が不安定
入力電圧では動作が不安定(入力電圧に対し、出力電流は指数関数的に変化する)
動作が安定する
入力抵抗を追加して入力を電流(ベース電流:IB)にすると動作が安定する。(入力電流に対し、出力電流はリニアに変化する)
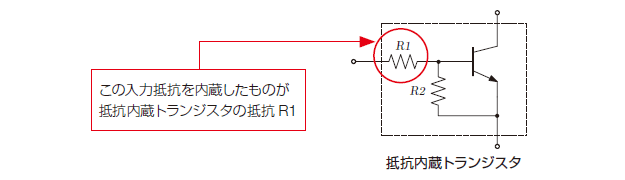
入力が電圧の場合と、電流の場合のトランジスタの動作を比較します。
|
電圧制御 入力:エミッタ- ベース間電圧VEB |
電流制御 入力:ベース電流IB |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Is:デバイスによって決まる定数 指数関数的に変化 |
hFE:増幅率 リニアに変化 |
|
|
|
|
入力- 出力特性を見ると、右側の電流制御では出力は入力に対してリニアに変化しているのに対して、 左側の電圧制御では出力は入力に対して指数関数的に変化することがわかります。 つまり、電圧制御では、ごくわずかな入力の変化で出力電流が大きく変化してしまい、動作が不安定になってしまいます。 例えば、右側のグラフでは、入力電流が40 μ A から80 μ A に2 倍変化したときに出力電流は9mA から18mA に2 倍になりますが、 左側のグラフでは入力電圧が0.7V から0.8V にわずか14%だけ変化しただけで出力電流は10mA から70mA に7 倍にもなってしまいます。 これでは、入力電圧にわずかなノイズが入っただけで出力電流が大幅に変化してしまい、実際の使用には適しません。

このように、バイポーラトランジスタは電流制御のほうが安定するため、ICからの電圧出力をベース電流に変換するのに入力抵抗R1が必要になります。デジトラはこのR1を内蔵しているので、部品点数やスペースの削減に適しています。
(2)抵抗R2 について
抵抗R2 の役割:リーク電流を吸収し、誤動作を防ぐことにあります。 抵抗R2 は、入力側から入ってくるリーク電流やノイズなどをグランドに落とすことでトランジスタの誤動作を防ぎます。
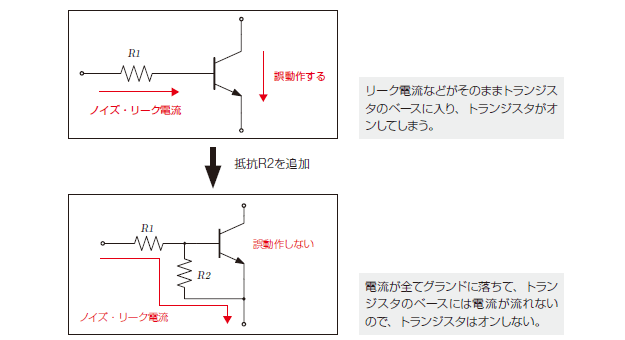
微小な電流なら入力電流は全てグランドに落ちますが、入力電流が大きくなると、入力電流の一部がトランジスタのベースに入りはじめ、トランジスタがオンします。
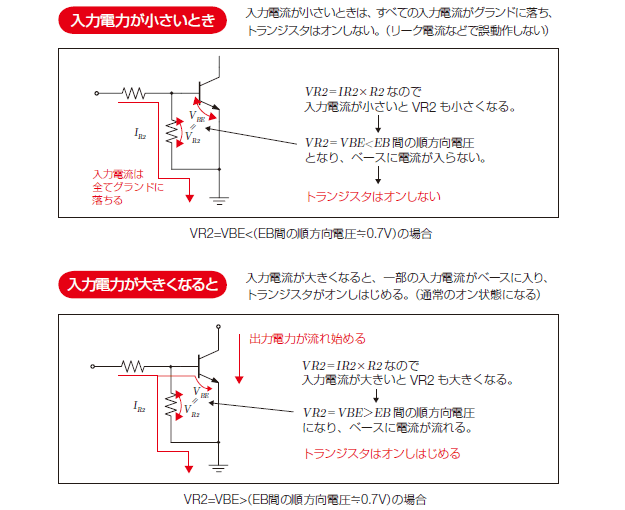
このように、抵抗R2 によって安定動作が実現されますが、トランジスタをオンさせるためにある一定以上の電圧が必要になります。