43. 抵抗内蔵トランジスタの計算方法
トランジスタとも呼ばれます。
(1)ベース電流の計算
ベース電流の計算を実際の抵抗内蔵トランジスタを例に以下で説明します。
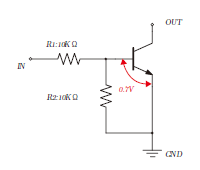
抵抗内蔵トランジスタの動作時には内蔵トランジスタのエミッタ-ベース間(EB間)の順方向にベース電流が流れているため、EB間には順方向電圧(25℃で約0.7V)
がかかっています。抵抗内蔵トランジスタでは内蔵トランジスタのEB間と抵抗R2が並列に接続されているため、R2にも同じ0.7Vが印加されています。従って、R2には![]() の電流が流れていることが分かります。
の電流が流れていることが分かります。
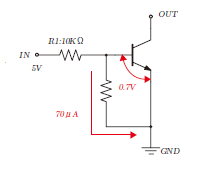
入力電圧Vinが5Vの場合、IN端子の電位が5Vで、内蔵トランジスタのEB間電位差が0.7Vなので、抵抗R1の両端には![]() の電圧がかかっていることが分かります。従って、R1には
の電圧がかかっていることが分かります。従って、R1には![]() の電流が流れていることが分かります。
の電流が流れていることが分かります。
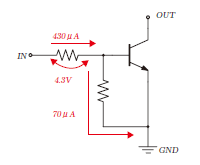
従って、内蔵トランジスタのベースには![]() の電流が流れていることが分かります。
の電流が流れていることが分かります。
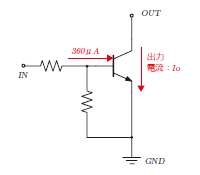
このような計算で内蔵トランジスタに流れるベース電流を計算することができます。抵抗内蔵トランジスタを十分にオンさせる(=出力電圧Vo(on)を小さくする)には出力電流 Io が内蔵トランジスタに入るベース電流の10~20倍程度以下になるように出力電流 Ioや入力電圧Vinを調整してください。入力電圧Vinが足りなくて、 十分な出力電流を流せない場合は、入力抵抗R1の小さいタイプの抵抗内蔵トランジスタをご使用ください。
(2)最低必要な入力電圧(駆動電圧)の計算
抵抗内蔵トランジスタをオンさせるための入力電圧(駆動電圧)を、実際の抵抗内蔵トランジスタを例に以下で説明します。
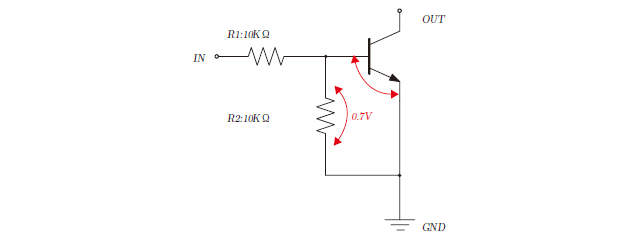
抵抗内蔵トランジスタの動作時はEB間に順方向電流が流れているので、(EB間電圧)=(EB間順方向電圧:約0.7V)=(R2の両端にかかる電圧)が成り立ちます。
抵抗内蔵トランジスタの動作時には内蔵トランジスタのエミッタ-ベース間(EB間)の順方向にベース電流が流れているため、EB間には順方向電圧(25℃で約0.7V)がかかっています。抵抗内蔵トランジスタでは内蔵トランジスタのEB間と抵抗R2が並列に接続されているため、R2にも同じ0.7Vが印加されています。従ってR2には![]() の電流が流れていることが分かります。
の電流が流れていることが分かります。
このR2に流れている70μAは、R1にも流れています。従って、R1の両端には![]() の電圧がかかっていることが分かります。このR1の0.7Vと、内蔵トランジスタのEB間の0.7Vを合わせて、抵抗内蔵トランジスタをオンさせるためには合計1.4Vの入力電圧が必要なことが分かります。
の電圧がかかっていることが分かります。このR1の0.7Vと、内蔵トランジスタのEB間の0.7Vを合わせて、抵抗内蔵トランジスタをオンさせるためには合計1.4Vの入力電圧が必要なことが分かります。
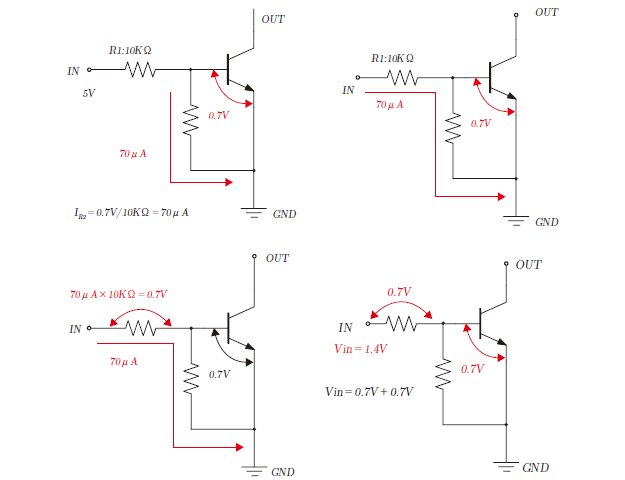
以上より、抵抗内蔵トランジスタをオンさせる電圧Vi(on)を一般化すると、順方向電圧をVfとして![]() となります。この結果から、抵抗内蔵トランジスタのオン電圧はR1とR2の比率で決まることが分かります。
となります。この結果から、抵抗内蔵トランジスタのオン電圧はR1とR2の比率で決まることが分かります。
実際には抵抗値比率とVfのばらつきによって上記の駆動電圧は20~30%程度のばらつきがあるほか、温度変化による変動もありますのであくまでも目安とし、実際にご使用の際は十分なマージンを確保して設計してください。正確には、25℃においては出力電流が100μA程度の場合は![]() 程度で、出力電流が1mA程度の場合は
程度で、出力電流が1mA程度の場合は![]() 程度を目安に計算してください。
程度を目安に計算してください。
以上で計算した電圧はあくまでもオンし始める電圧です。実際にある程度の出力電流を流すためには、上記の条件の他に出力電流の1/20程度以上の電流を内蔵トランジスタのベースに入れる必要がありますので必要な入力電圧はもっと大きくなります。以上の例ではnpn型で考えましたが、pnp型でもVfの値がほとんど同じなので同様の計算が成り立ちます。
