44. サイリスタとトライアックの基本動作
いずれも電力制御用途に向けた整流素子です。
ただし、サイリスタは一方向制御素子なのに対して、
トライアックは双方向制御素子である点が異なります。
サイリスタの基本動作
サイリスタ(Thyristor)は、ゲート(G)からカソード(K)にゲート電流を流すことにより、アノード(A)とカソード(K)間を導通させることができる3端子の半導体整流素子です。SCR(Silicon Controlled Rectifier)とも呼びます。構造は、p型、n型、p型、n型の順番に半導体を積層したpnpn構造を採用します。p型半導体からゲート端子を引き出す素子をpゲート品、n型半導体からゲート端子を引き出す素子をnゲート品と呼びます。原理としては、図のようにpnpトランジスタとnpnトランジスタを組み合わせた複合回路と等価になります。動作の様子を詳しく見てみましょう。ゲートから一定の電流を流すと、アノードとカソードの間が導通(ターン・オン)して、そのまま導通状態が続きます。導通状態を停止(ターン・オフ)させるには、アノードとカソードの間の電流を一定値以下に下げる必要があります。こうした特長を生かし、一度導通状態に移行させたら、通過電流がゼロ(0)になるまでその導通状態を維持する必要がある用途で使われています。
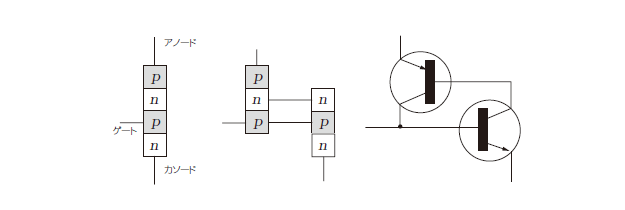
トライアック
サイリスタは、一方向のオン/オフ制御を実現する素子ですが、これを双方向のオン/オフ制御が可能なように改良した素子がトライアック(TRIAC)です。トライアックは、2個のサイリスタを逆並列に接続し、双方向に電流を流せるようにした素子です。交流でも直流でも使用可能です。ただし、実際には単純にサイリスタを2個接続して構成しているのではなく、図に示すようにモノリシック構造になっています。なお、トライアック(TRIAC)は1964年に米GeneralElectric(ゼネラル・エレクトリック)社が業界に先駆けて発売した際の製品名である「Triode AC Switch」を略したものです。

| 用 語 | 略号 | 単位 | 説 明 |
|---|---|---|---|
|
ピーク繰り返しオフ電圧 |
|
V |
A-K間に繰り返しかけられる最大電圧値 |
|
ピーク繰り返し逆電圧 |
|
V |
A-K間に繰り返しかけられる逆電圧の最大電圧値 |
|
ピーク非繰り返しオフ電圧 |
|
V |
A-K間に繰り返しでなくかけられる最大電圧値 |
|
ピーク非繰り返し逆電圧 |
|
V |
A-K間に繰り返しでなくかけられる逆電圧の最大電圧値 |
|
平均オン電流 |
|
A |
連続して流せるオン電流の平均値 |
|
実効オン電流 |
|
A |
連続して流せるオン電流の実効値 |
|
ピークゲート損失 |
|
W |
ゲート消費電力の最大瞬間値 |
|
平均ゲート損失 |
|
W |
耐えられるゲート消費電力の平均値 |
| 用 語 | 略号 | 単位 | 説 明 |
|---|---|---|---|
|
ピーク・ゲート順電圧 |
|
V |
G-K間に繰り返しかけられるゲート電圧の最大瞬間値 |
|
ピーク・ゲート逆電圧 |
|
V |
G-K間に繰り返しかけられるゲート逆電圧の最大瞬間値 |
|
ピーク・ゲート順電圧 |
|
A |
G-K間に繰り返しかけられるゲート電流の最大瞬間値 |
|
ピーク・オン電圧 |
|
V |
オン状態の時にA-K間にかけられる電圧の最大値 |
|
ゲート・トリガ電流 |
|
V |
オンさせるために必要な最小ゲート電圧 |
|
ゲート・トリガ電流 |
|
A |
オンさせるために必要な最小ゲート電流 |
