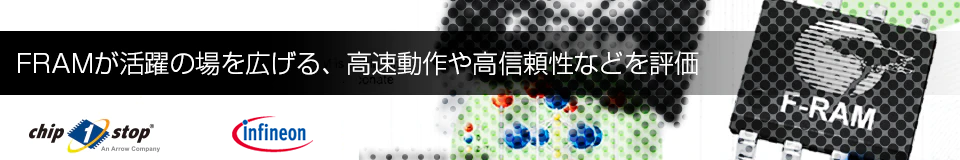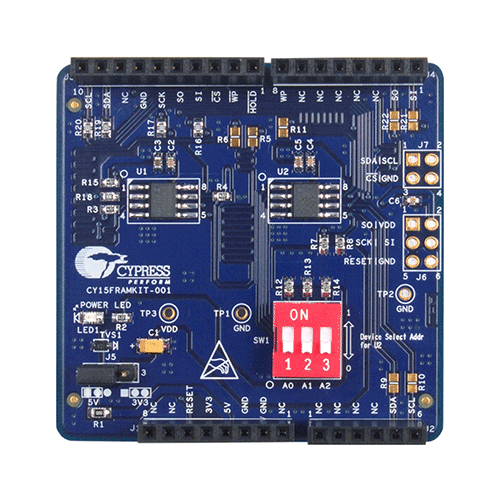※このインタビュー記事は、2017年12月に掲載した内容です。
 伊藤和志 氏(左) 早瀨昭司氏 (右)
伊藤和志 氏(左) 早瀨昭司氏 (右)
電子機器にとって、メモリーは極めて重要なコンポーネントである。スマートフォンにも、テレビにも、電気自動車(EV)にも、たくさんのメモリーが搭載されている。メモリーなくして、電子機器は動作しない。
ただし、一口にメモリーと言っても、その種類は非常に多い。プログラムを常時格納しておくメモリーや、演算結果を一時的に蓄えるメモリー、音声や映像といった大容量データを収めるメモリーなどを搭載する必要がある。プログラムを常時格納しNOR型フラッシュEEPROM(フラッシュ・メモリー)などが、演算結果を一時的に蓄えるメモリーにはDRAMなどが、音声や映像といった大容量データを収めるメモリーにはNAND型フラッシュ・メモリーなどが使われる。つまり、電子機器を設計する際には、用途を応じて最適なメモリーを選び、組み込まなければならないわけだ。
サイプレス セミコンダクタ(Cypress Semiconductor)も、そうしたメモリーを提供している半導体メーカーの1社だ。同社が得意とするのは、電源を切ってもデータを保持し続けられる不揮発性メモリーである。今回は、同社のMPD マーケティング本部で本部長を務める伊藤和志(いとう・かずし)氏と、リージョナルマーケティング(MPD)でシニアマネージャーを務める早瀨昭司(はやせ・しょうじ)氏に、最近力を入れている製品や、その製品の特徴、マーケットの状況などについて聞いた
(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。
最近、特に力を入れている製品は何か。
伊藤 当社の強みは、不揮発性メモリーにある。SRAMとEEPROMを組み合わせた当社独自の不揮発性SRAM「nvSRAM」のほか、FRAM(強誘電体メモリー)やNOR型フラッシュ・メモリーなどを手掛けている。この中でも、最近、開発や製品化、販売などに特に力を入れているのはFRAMとnvSRAMだ。
FRAMの現状を教えてほしい。
伊藤 当社は、FRAMの開発で業界をリードしてきた米Ramtron International社を2012年11月に買収しており、現時点ではFRAMのトップ・ベンダーである。今、このFRAMの活躍の場が拡大している。従来から使われていた電力メーターや多機能プリンター(MFP)のほかに、医療機器、車載機器や産業機器などにも採用が広がっている。
市場が広がっている理由は何か。
伊藤 理由は、FRAMが備える特徴にある。その特徴を説明する前に、簡単にFRAMの原理を説明したい。
FRAMは、強誘電体という材料の特性を利用してデータを書き込むメモリーである。具体的には、強誘電体材料の分極という現象を利用する(図1)。強誘電体薄膜に、外部から電圧(電界)を与えると、薄膜内部で分極が発生する。これは、電源(電圧)を切っても保持できる。従って、不揮発性メモリーを実現できるわけだ。しかも分極現象は非常に安定しており、外部から温度や放射線を与えても、データは書き換えられない。従って、極めて信頼性の高いメモリーを実現できるわけだ。
多くの長所を持つFRAM
メモリーの特性としては、どのようなメリットがあるのか。
3つの長所について、簡単に説明してほしい。
伊藤 アクセス時間が短いことは、SRAMと同様に、ランダム・アクセスとオーバーライトが可能ことに起因する。フラッシュ・メモリーやEEPROMは、イレース(消す)して、書き込む(ライト)という複数の作業が必要だった。しかも、FRAMはバイト単位でのオーバーライトが可能だ。フラッシュ・メモリーやEEPROMは、複数のバイトの集合体であるページ(ロー)単位でしたイレース/ライトができなかった。このため、FRAMのアクセス時間は、SRAMの10nsには及ばないものの、55nsと短い。一方、フラッシュ・メモリーは100ns、EEPROMは5msも掛かっていた。
2つめの書き換え回数が多い理由は、強誘電体材料の分極現象を利用してデータを書き込んでいる点にある。分極による材料の劣化(分極反転疲労)の程度は非常に小さいからだ。このためFRAMの書き換え回数は1014回に達する。つまりSRAMには若干劣るものの、ほぼ無制限と言って過言ではない。ちなみに、フラッシュ・メモリーは105回、EEPROMは106回である。こうした回数では、データを頻繁に書き換える用途では、すぐに寿命が来てしまう。
3つめのデータ保持時間が長い理由も、分極現象を利用していることに起因する。分極は非常に安定した現象であり、仮に放射線や宇宙線が飛び込んできても、ビットが入れ替わることはない。FRAMのデータ保持期間は100年と極めて長い。フラッシュ・メモリーやEEPROMは長くても10年から15年程度だ。
逆にデメリットや短所はないのか。
大容量化の取り組みについて教えてほしい。
伊藤 製造技術の微細化を進めることで、大容量化する考えだ。すでに16Mビットまでは実現できるメドが立っている。2018年には製品化できるだろう。
車載機器での採用が進む
FRAMはどのような用途で使われているのか。
伊藤 これまでは、多くの書き換え回数が要求されると同時に、データ保持に高い信頼性が求められる用途に使われていた。具体的には、電力の使用状態を積算していく電力メーターや、カウンターに課金情報を書き込む多目的プリンターなどだ。さらに、Blu-ray DiscレコーダーやHDDレコーダーにおいて、電源を切った際の再生ヘッドの一を記憶させるレジューム機能でFRAMが使われている。
このほか、補聴器に搭載するDSPのワーク・メモリーとしても使われている。FRAMは、フラッシュ・メモリーとは違い、書き込み時に高い電圧を必要としない。このため補聴器のような小型の電池駆動機器にも搭載可能だ。
最近増えてきた用途には、どのようなものがあるのか。
伊藤 車載機器での採用が増えている。例えば、カーナビ装置。エンジンを切ったときに、その地点の位置情報を格納しておく用途で使われている。こうすれば、リスタートしたときに、即座に現在位置を表示できる。GPS信号を受信して現在位置を取得しようとすると、数秒程度かかってしまい、すぐには表示できない。
さらに、シートに座った乗員をセンシングして、エアバッグの爆発量を最適制御する「スマート・エアバッグ」でも、乗員のデータを格納する用途でFRAMが活用されている。
早瀨 産業機器でも採用が進んでいる。例えば、サーボ・モーター搭載機器で、電源を切った瞬間のモーターの位置を記憶しておく用途である。産業機器は、製品寿命が長く、25年や30年も使われることがある。FRAMであればデータ保持期間が100年と長いため、信頼性を確保できるわけだ。さらも、携帯型の医療機器でも、高電圧が不要な点が評価され、患者のライフログを格納する目的でFRAMが使われている。
アクセス時間が短いnvSRAM
最近特に力を入れている製品として、FRAMとともにnvSRAMを挙げていた。まずは、nvSRAMとはどのようなメモリーか説明してほしい。
nvSRAMの特徴は何か。
メモリー容量は最大でどの程度か。
伊藤 パラレル・インターフェース品であれば最大で16Mビットまで、LPC(Low Pin Count)バス品であれば1Mビットまで対応している。
nvSRAMの主なアプリケーションは何か。
早瀨 アクセス時間が短いことや、電池の交換が必要ないこと、電池を搭載していないため高温環境でも動作することなどが評価され、ネットワーク機器や産業機器、アミューズメント機器などに採用されている。