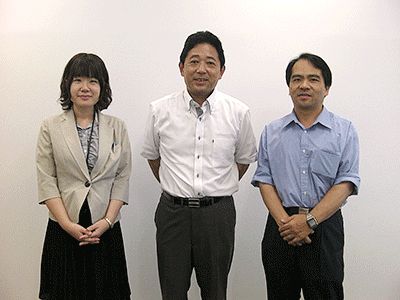村田製作所は、積層セラミック・コンデンサ(MLCC)やインダクタ、抵抗器、EMI対策部品などの受動(パッシブ)部品市場において、世界をリードする企業である。しかし、同社が手がけている製品は受動部品だけではない。電源や無線通信モジュール、センサ・デバイスなどの製品も取り組んでおり、技術力や製品力の強化を進めている。
その一環として同社は、異方性磁気抵抗(AMR:Anisotropic Magneto Resistive)センサに関する事業を2013年6月にNECから譲り受けた。このAMRセンサを使えば、磁界の微弱な変化を検出できる。この特徴を生かして、これまで給湯器や水道メータ、ガス・メータ、携帯電話機/ノート・パソコンの開閉検出などに使われてきた。
この高性能なAMRセンサを使って、どのような市場を開拓していくのか。同社においてAMRセンサを担当する今野秀人氏(センサ事業部 第2センサ商品部 担当次長)に、AMRセンサで得られる性能やターゲットとする市場、最新製品の特徴などについて聞いた(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。
これまでAMRセンサは、どのような用途に使われてきたのか。
今野 AMRセンサ自体は、40〜50年前から存在している。当社(NECの時代)が製品化したのは1980年代である。水量の遠隔検針を目的とした水道メータに採用した。仕組みは単純だ。水道メータの中に、羽に磁石を取り付けた水車を入れておき、その回転数をAMRセンサで読み取ることで水量を計測した。その後、給湯器、ガス・メータやオイル・メータにも展開した。
10年ぐらい前からは、液晶ディスプレイと本体をスライドさせて使用する携帯電話機の開閉検出に採用され、出荷数量は急拡大した。スマートフォンの普及とともに、その市場は小さくなってしまった。
回転数を測定したり、磁石の近接を検出したりするセンサとしては、ホール効果センサがある。ホール効果センサとAMRセンサの違いは何か。
今野 当社では、AMRセンサのほか、InSb(インジウム・アンチモン単結晶)を用いたSMR(Semiconductor Magneto Resistive)センサも手がけている。しかし、ホール効果センサは手がけていない。
AMR/SMRセンサとホール効果センサは何が違うのか。c端的に言うと、検出可能な磁気の強さが違う。ホール効果センサは強い磁気の検出に、AMR/SMRセンサはそれよりも低い磁気の検出に向く。
また、細かな磁気記録(磁気の強弱でなく、記録自体が細かいかどうか)の検出にAMR/SMRセンサが向くのに対して、ホール効果センサはある程度の大きさが必要になるため向かない。
しかし、モーターの回転検出には、AMR/SMRセンサではなく、ホール効果センサが使われている。その理由は何か。
今野 ホール効果センサは、比較的簡単な工程で製造できる。このため価格が安い。それがモーターの回転検出に使われている最大の理由だ。しかし、前述のように微弱な磁界は検出できないうえに、温度特性が良好ではない、消費電力が大きいという欠点がある。こうした欠点をクリアしたい場合は、AMR/SMRセンサを使うしかない。
他社に真似できない製造
AMRセンサとSMRセンサの素子構成などを解説してほしい。
今野 AMRセンサは、信号処理回路と、パーマロイ(Ni-Fe、ニッケル鉄)から成るAMR素子をSi(シリコン)基板上に集積している。つまり、1チップ構成である。
ただし、かつては1チップと言っても、信号処理回路とAMR素子を横に並べて集積していた。これでは、実装面積が大きくなる。そこで最近では、信号処理回路の真上にパッシベーション膜を形成し、その上にAMR素子(厚さは0.03μm程度)を作り込む積層構造を採用している。こうすることで外形寸法を大幅に小型化できる。
最小の製品「MRMS601A」の外形寸法は、わずか1.0mm×1.6mm×0.37mmである。極めて小さい。
この製造プロセス技術を所有しているのは当社だけだ。通常、半導体メーカーは、NiやFeといった金属材料を製造プロセスに導入するのを嫌がる。ほかの回路に悪影響を与える危険性が高いからだ。しかし当社は、従来からこの製造プロセスの開発に取り組んでおり、さまざまなノウハウや知見を蓄積している。このため、当社だけが実現できるわけだ。
実際には、Si基板に信号処理回路を作り込む作業は、外部の半導体ファウンドリ企業に依頼している。当社では、そのSi基板の上にパッシベーション膜とAMR素子を形成する工程を担当している。
一方、SMRセンサはInSb単結晶を購入し、μmオーダーの薄板に加工し、それを信号処理チップとともに1チップに収める構造を採用している。
3Dセンシングが可能に
最新製品に関する情報を知りたい。
今野 最近市場に投入したAMRセンサの中に「MRMS591A」という製品がある。この製品の特徴は、360度全方位から印加される磁界を同じ感度で検出できる点にある。当社では、こうした検出を「3Dセンシング」と呼ぶ。一般的なAMRセンサでは一方向の検出しかできない。
用途としては、例えばアミューズメント機器の不正防止がある。磁石を近づける不正が行われる場合、どの方向から磁界を印加されるかわからない。従来であれば、ホール効果センサを5個程度使う必要があった。今回の製品を使えば、1個で済む。外形寸法は1.45mm×1.45mm×0.55mmと小さいため小型化が可能な上に、低コスト化も図れる。磁束密度の検出範囲は0.8m〜6.0mTである。
どうやって360度全方位の検出を可能にしたのか。
今野 詳細は明らかにできない。搭載したAMR素子の構造と、信号処理回路を工夫することで実現した。
このほかにも、特徴的な製品を紹介してほしい。
今野 消費電力が極めて小さいAMRセンサ「MRUS74」がある。サンプリング時間を1μsと短くすることで、消費電流を0.3μAに削減した。外形寸法は1.5mm×1.8mm×0.8mmで、磁束密度の検出範囲は1.0m〜2.5mTである。すでにガス・メータやセキュリティ機器などに採用されている。
例えば、セキュリティ機器では、キーレスのドアロック機構に使われている。カード・キーをリーダーにかざすと、ドアのカギが開く。MRUS74は、このカギが正常に動作したかどうかを検出する役割に使われている。消費電流が極めて小さいため、小型電池で数年動作させることが可能だ。
世の中にないセンサを売り出したい
今後、特に注力するAMR/SMRセンサのターゲット市場は何か。
今野 医療/ヘルスケアと、自動車、エネルギ(バッテリ)を3つの柱として、市場を開拓していく考えだ。
将来の製品展開について教えてほしい。
今野 まずは、対応できる磁界(磁束密度)の領域を広げることで、品ぞろえを増やしていきたい。特に、注力したいのは、より微弱な領域である。現時点では詳細は明らかにできないが、地磁気よりも微弱な磁界を検出できる新しい磁気センサの開発に取り組んでいる。これが実用化されれば、対応可能な磁界領域は大きく広がることになる。
さらに将来的には、さまざまなセンサを1パッケージに収めたモジュール品を実用化したい。現在、ウエアラブル機器には、方位センサや気圧センサ、加速度センサ、角速度センサ(ジャイロスコープ)などが搭載されている。これらをすべて1チップに集積するのは困難だが、モジュール化するのは可能だろう。半導体技術やアセンブリ技術の力を借りながら、使い勝手が高く、性能に優れた「世の中にないセンサ」を売り出したい。
AMRセンサ (磁気スイッチ)
| 項目 | リードスイッチ | AMRセンサ | ホールIC |
|---|---|---|---|
| サイズ(コンパクト性) | × | ○ | ○ |
| 耐振動 | × | ○ | ○ |
| 耐衝撃 | × | ○ | ○ |
| 設計自由度 | △ | ◎ | △ |
| 製品寿命 | × | ○ | ○ |
| 感度バラつきの少なさ | × | ◎ | × |
| 検出磁石のサイズ(コンパクト性) | × | ◎ | × |
【用途】
・開閉検知
パネルの蓋の開け閉め確認
冷蔵庫内の灯りのON/OFFによる省エネ
ケイタイ/パソコンの液晶画面のON/OFFによる省エネ)
・回転検知
DVC液晶画面の“自分撮り”モードの際の反転検知
ガスメーターのギアの回転を検知してガス流量を計測
水道メーターの羽根車の回転検知して水の流量を計測
・位置検知
防犯用窓:窓が開くことでアラームが鳴る
エアシリンダのピストンの正常移動を確認
工程センサ-:油圧ステージ移動距離測定