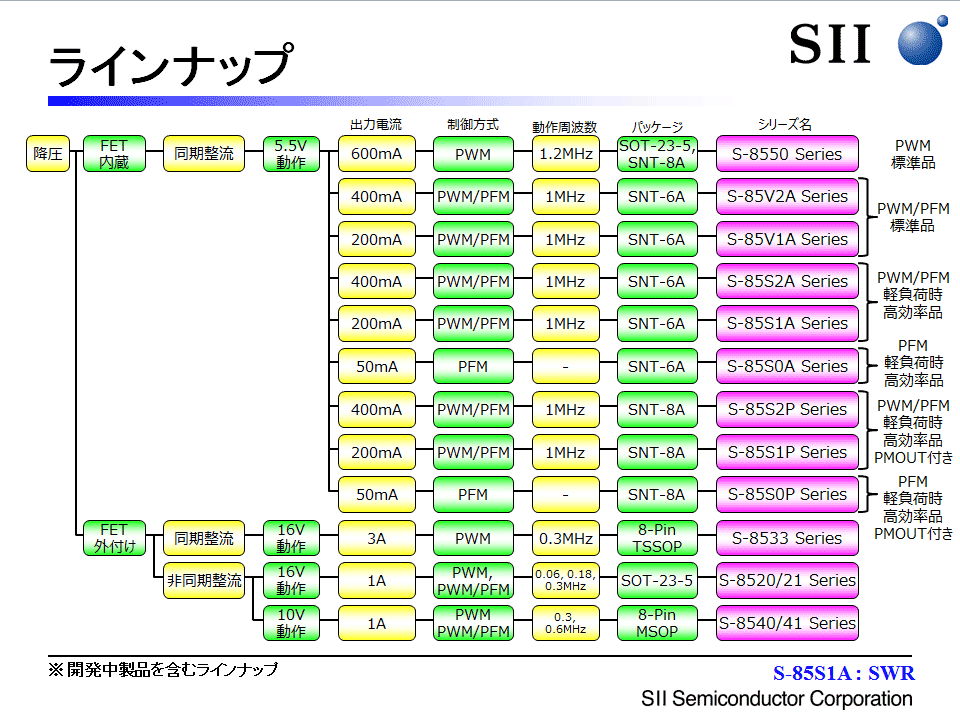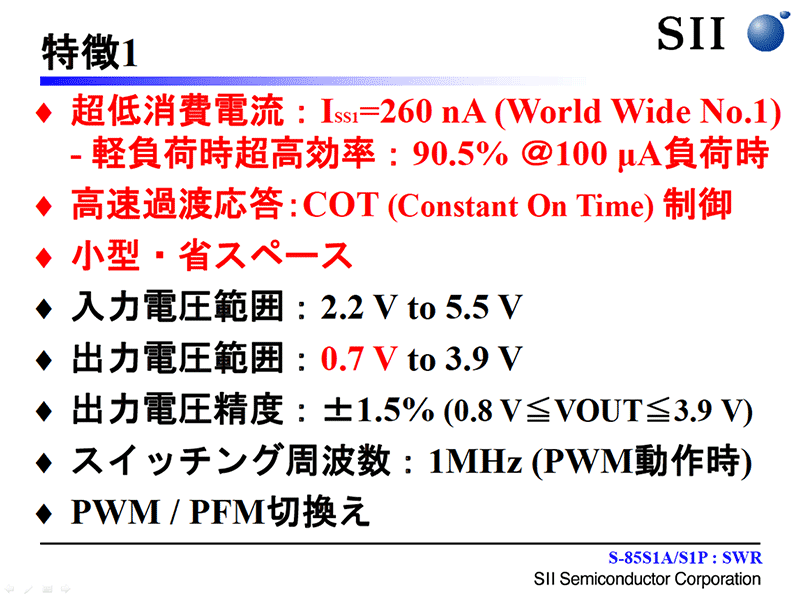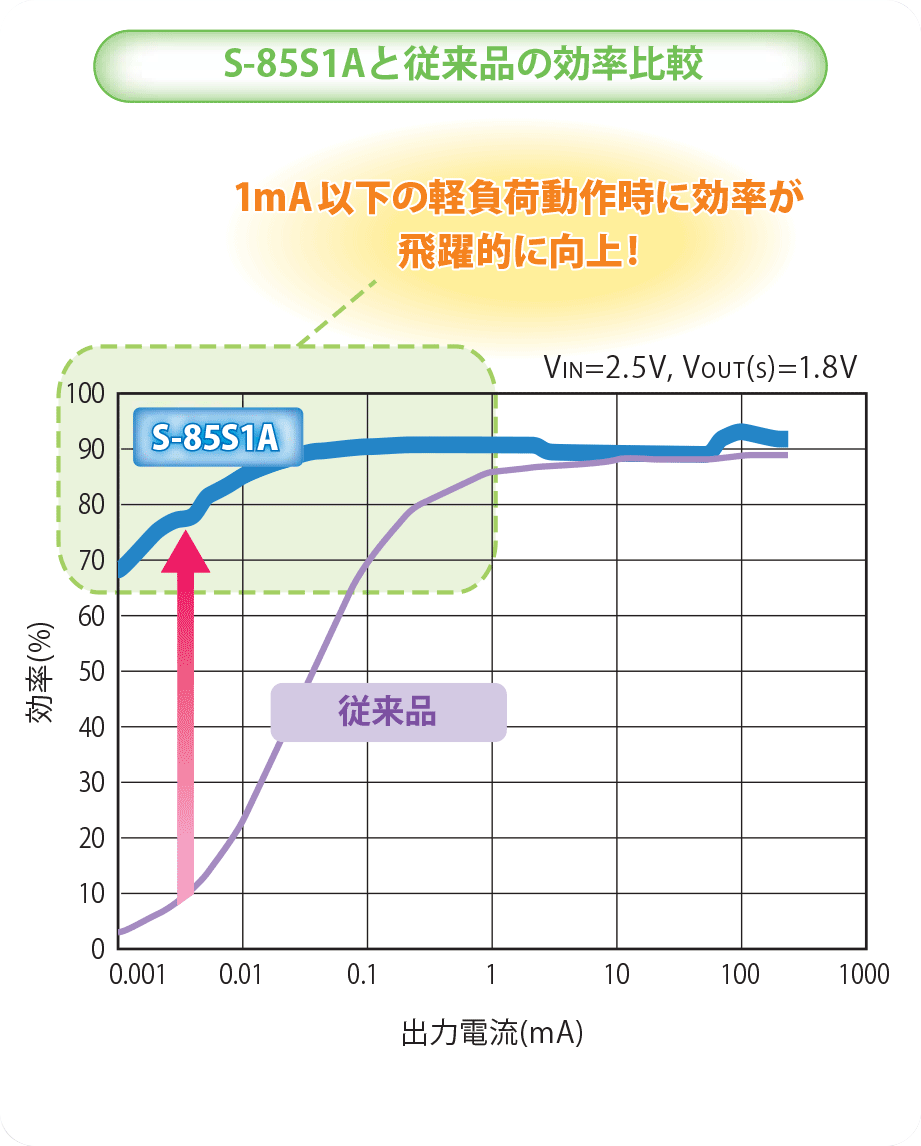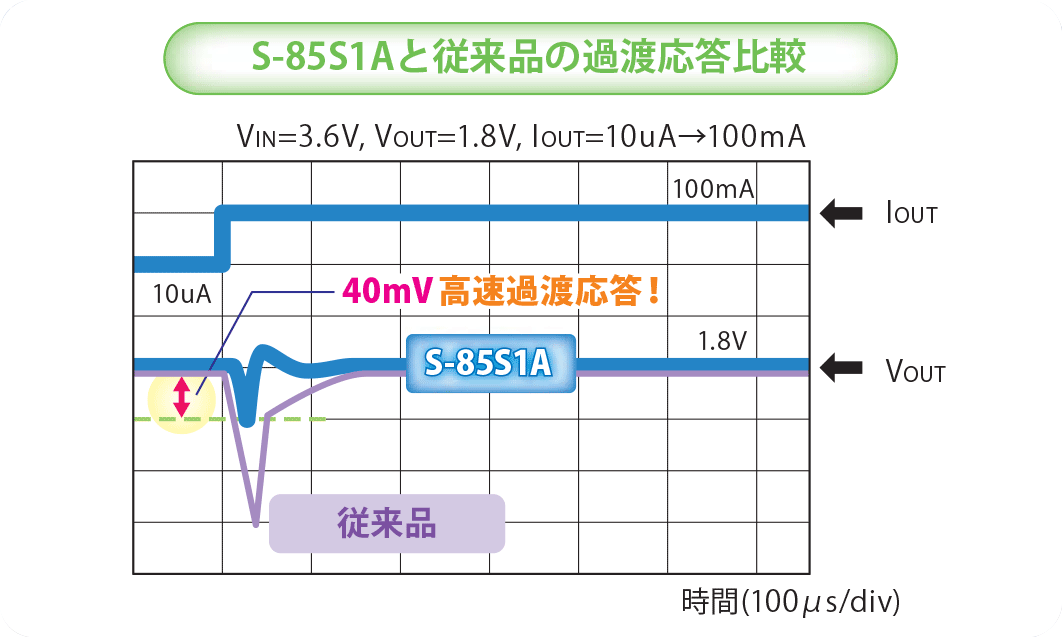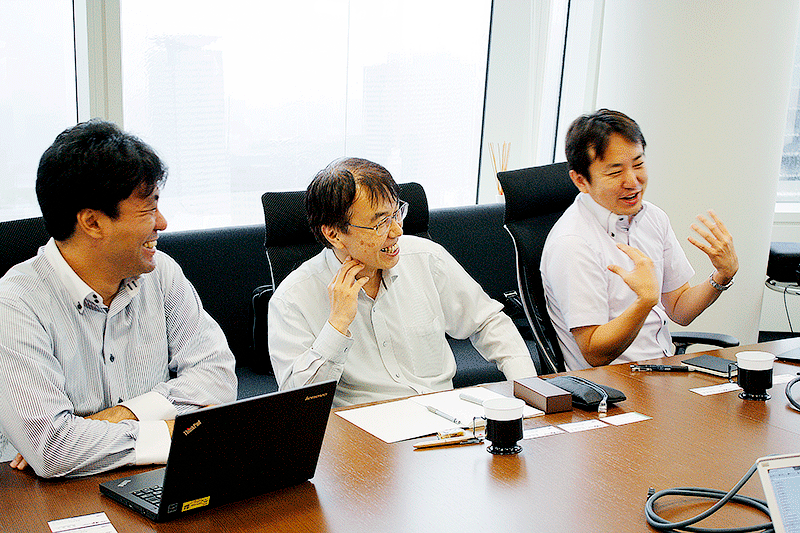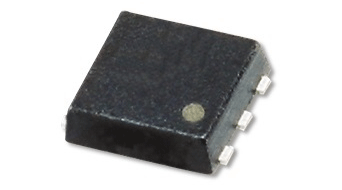商品開発一部 開発三課主任 企画担当 小澤貴一 氏(左)
商品開発一部 開発三課主任 企画担当 小澤貴一 氏(左)商品開発一部 部長 須藤稔 博士(工学)
商品開発一部 開発三課長 和気宏樹 氏(右)
携帯型電子機器やウエアラブル機器、IoT機器にとって、電池駆動時間は極めて重要な性能である。電池の交換や充電が頻繁に必要になるようでは、製品価値を高めることができないからだ。例えば、1個のコイン電池だけで、2年や3年といった長い期間駆動し続けられるような設計が求められる。
それには、少しでもエネルギー容量の大きな電池を採用したり、消費電力の小さいマイコンや無線通信チップなどを搭載したりすることが求められる。しかし、長い電池駆動時間を実現するには、これだけでは不十分だ。実は、電池の出力電圧を、マイコンなどの動作に最適な電圧に変換する電源(DC-DCコンバーター)回路の低消費電力化も欠かせない要素だ。
こうした用途に向けて、エスアイアイ・セミコンダクタは、静止時消費電流を260nAに削減した降圧型DC-DCコンバーターIC「S-85S1A/S-85S1Pシリーズ」を開発し、製品化した。今回は、このICの開発やマーケティングに携わっている商品開発一部 部長の須藤稔(すどう・みのる)氏と、商品開発一部 開発三課長の和気宏樹(わけ・ひろき)氏、商品開発一部 商品三課主任 企画担当の小澤貴一(おざわ・たかかず)氏に、開発の背景や製品の特徴、技術的なポイント、販売戦略などについて聞いた(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)
新しい降圧型DC-DCコンバーターICの開発に着手したきっかけは何か。
小澤 スマートウォッチや、スマートグラス、補聴器などのウエアラブル機器に向けて、とにかく消費電力の少ない降圧型DC-DCコンバーターICを製品化することを目的に開発をスタートさせた。実際に、完成させてユーザーに紹介して歩いたところ、IoT機器ベンダーからの引き合いも予想を上回るほど多かった。
S-85S1A/S-85S1Pはどのような降圧型DC-DCコンバーターICなのか。簡単に説明してほしい。
小澤 同期整流方式を採用した降圧型DC-DCコンバーターICである(図1)。スイッチング素子はハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチとも集積した。入力電圧範囲は+2.2〜5.5V(図2)。出力電圧は+0.7〜3.9Vの範囲で、ユーザーが購入時に50mVステップで指定できる。当社は、レーザー・トリミングで指定された出力電圧値に合わせて出荷する。最大出力電流は200mA。スイッチング周波数は1MHzである。
最大の特徴は何と言っても、静止時消費電流が260nAと極めて少ないことだ。業界で最も少ない値だ。100μAの軽負荷時であっても変換効率は90.5%と高い(図3)。実は、出力電流がもっと少ないケースでも、かなり高い変換効率が得られる。例えば、10μA出力の場合は約85%、1μA出力の場合は約70%である。一般的な製品であれば、10μA出力の場合は20%程度の効率しか得られないだろう。
フィードバック・ループの制御方式は何か。
須藤 コンスタント・オン・タイム(COT)方式を採用した。いわゆる、ボトム検出オン時間固定方式である。この方式を採用したため、負荷過渡応答特性に優れるというメリットがある。例えば、出力電流が10μAから100mAに変化したときに、出力電圧(+1.8V)の変動率を2.2%に抑えられる(図4)。競合他社品の変動率は6.7%と大きい。
回路構成の工夫で実現
どうやって低消費電流化を実現したのか。
和気 回路構成を工夫したことで低消費電流化を達成した。具体的には、デジタル回路では一般的になっている「パワー・ゲーティング」技術をアナログ回路に持ち込んだ。パワー・ゲーティングとは、必要なときに必要な回路ブロックだけを動かし、それ以外の回路ブロックは止めておくという技術だ。必要最小限の回路だけを動かせばいいので、消費電流を低減できる。
ただし、これをアナログ回路に適用するのはかなり難しい。アナログ回路自体はかなり高速で動作しているため、どのタイミングでどの回路を動かせば、必要な機能を実現しながら、電流消費を最小限に抑えられるのか。そのタイミングや、バランスを解き明かすのに苦労した。
製造プロセス技術に関する工夫はあるのか
静止時消費電流を競合他社品と比べると、どのような関係になるのか。
小澤 当社の製品は、業界で最も低い。例えば、国内の競合企業に比べると約48%減、海外の競合企業に比べると約18%減を実現している*1)。
*1)静止時消費電流の比較については、エスアイアイ・セミコンダクタの調査結果に基づく。
パワー・モニター機能も搭載
このほかに特徴はあるのか。
須藤 パワー・モニター機能を搭載していることが上げられるだろう(S-85S1Pのみに搭載)。一般に、コイン電池やリチウムイオン2次電池などの電池残量を簡易的に把握するには、電池の端子電圧を監視(モニター)する。電池は、エネルギー容量が少なくなるにしたがって、端子電圧が低くなる特性を持っているからだ。ただし、電池の中には端子電圧が3Vを超えるものもある。低電圧で動作するマイコンなどには直接入れることはできない。そこで通常は、端子電圧(DC-DCコンバーターICの入力電圧)を、抵抗分圧回路を使って低くしてマイコンのADC(A-D変換)端子などに入力している。
抵抗分圧回路は、通常2個の抵抗器で構成する単純なものだが、その設計は決して簡単ではない。抵抗分圧回路での消費電流を減らすには、抵抗値の高い抵抗器で構成すればいいが、それではインピーダンスの関係で低電圧マイコンのADC端子には直接接続できなくなってしまう。抵抗値の低い抵抗器で構成すればマイコンに直接接続できるようになるが、抵抗分圧回路での消費電流が増えてしまう。このインピーダンスと消費電流を最適化する設計作業は、かなり難しいと言えるだろう。
この問題をどのようにして解決したのか。

図5 高速負荷応答特性
コンスタント・オン・タイム(COT)制御方式を採用したため、
高い負荷過渡応答特性を実現した。
例えば、出力電流が10μAから100mAに変化したときに、
出力電圧(+1.8V)の変動率を2.2%(40mV)に抑えられる(図4)。
競合他社品の変動率は6.7%と大きい。
須藤 ICの中に高抵抗の抵抗器による分圧回路を集積した(図5)。そして、その後段にバッファ回路を入れることでインピーダンスを下げている。このため低電圧マイコンのADC端子に直接入力することが可能になった。高抵抗の抵抗分圧回路を使ったため、パワー・モニター機能の消費電流は280nAと少ない。DC-DCコンバーターの静止時消費電流である260nAを加えても、トータルの消費電流はわずか540nAである。
小澤 さらに、抵抗分圧回路をICに集積したため、基板上の実装面積を削減できるというメリットも得られる。想定する用途がウエアラブル機器やIoT機器であるため、抵抗分圧回路分の面積削減でもかなり大きなメリットだと言えるだろう。
なおS-85S1Pのパッケージは、外形寸法が1.57mm×2.46mm×0.5mmのSNT-8Aである。外付け部品を含むDC-DCコンバーター回路全体の実装面積は2.4mm×5.7mmで済む。
製品ラインナップを拡充へ
今後の製品展開について教えてほしい。
小澤 降圧型DC-DCコンバーターICのユーザーは多種多様だ。より大きな負荷電流を必要とするユーザーもいれば、少なくても構わないユーザーもいる。さらに、機器の小型化に伴い、実装面積を少しでも小さくすることを望むユーザーもいる。こうしたユーザーのさまざまな要望に応えるべく、今後、製品ラインナップを拡充する考えである。
例えば、今回の軽負荷時高効率品において、最大出力電流が400mAと大きい製品や、さらに50mAと小さい製品を投入する予定である。50mA品は小型の外付け部品と組み合わせることで実装面積をさらに小さくすることが可能になる予定だ。
和気 技術的には、最大出力電流が1Aや2Aと大きい製品も実現可能である。今後、製品化を検討していきたい。
米国のアナログ半導体メーカーは、付加価値の高い高性能な製品を開発し、その付加価値に応じた価格を設定している。
今回のICは、米国メーカーの製品を上回る性能を達成している。どのような価格戦略を立案しているのか。
小澤 この製品の付加価値に見合った価格設定をしたいと考えている。今回のICを使えば、電池駆動時間を大幅に延ばせる。電池駆動時間の課題を抱えている技術者なら、喜んで使ってもらえるはずだ。