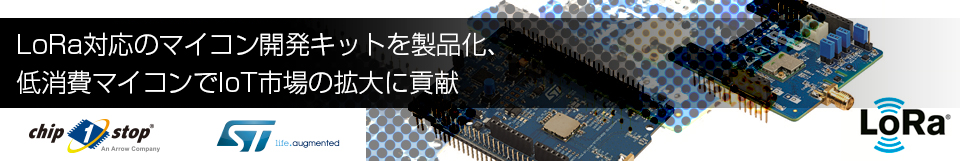原 文雄 氏
原 文雄 氏
IoT(アイ・オー・ティー)…。この3つのアルファベットを聞かない日はないぐらい、IoT(Internet of Things)技術の認知度は高まっている。しかし実用化の観点で見ると、普及段階に達したとは言い難い状況にある。広く普及させるには、ハードウエア技術の開発はもちろんのこと、ソフトウエアやアプリケーション、サービスなどの開発がまだまだ必要な段階だろう。
スイスに本社を置くSTマイクロエレクトロニクス(STMicroelectronics)社は、IoTの実用化や普及に向けて、技術開発や製品開発に精力的に取り組んでいる大手半導体メーカーである。現在同社は、長距離伝送が可能な無線通信技術「LoRa」に対応した低消費電力マイコン搭載の開発キットを提供中である。そこで今回は、STマイクロエレクトロニクス社の日本法人で、マイクロコントローラ・メモリ・セキュアMCU製品グループ マイクロコントローラ製品部 部長を務める原 文雄(はら・ふみお)氏に、LoRa技術を選んだ理由や、開発キットの特徴、IoT普及の現状などについて聞いた
(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。
IoTシステムの構築に不可欠な無線通信技術として「LoRa(Long Range)」を選んだ理由は何か。
原 IoTシステムでは、センサーやマイコンなどを搭載したIoTノードと、ゲートウエイ機器との間を無線通信技術で接続する。IoTノードは小型/軽量であり、さまざまな場所に設置される。このため、大きなバッテリーは搭載できず、AC電源を供給するわけにもいかない。従って、IoTノードに適用する無線通信技術には、低消費電力であることが必須である。
そうした観点から、当社の超低消費電力マイコンを無線通信技術のLoRaに対応させた。ただし、勘違いしないでほしい。LoRaだけを選択したわけではない。当社としては、BLE(Bluetooth Low Energy)、Wi-SUNなどの有望な無線通信技術も評価しており、実際にサポートしている。
LoRaとはどんな技術なのか、簡単に説明してほしい。
原 LoRaは、米国のファブレス半導体ベンダーであるSemtech(セムテック)社が開発したものだ。1GHz未満の周波数帯域、いわゆる「サブGHz帯」を利用する。日本ならば920MHz帯、米国ならば915MHz帯、欧州ならば863MHz帯などが使える。通信技術としては、スペクトラム拡散技術を利用する。こうすることで長距離伝送が可能な上に、極めて低い消費電力を実現している。
実際にどの程度の距離を飛ばせるのか。そのときの消費電力はどの程度なのか。
原 通信距離は、理論上30kmに達する。消費電力については、コイン型電池で10年以上の駆動が可能だ。いずれもIoTノードにとって重要な特性である。一方でデータ伝送速度は300ビット/秒〜30kビット/秒で、あまり高くない。
Semtech社とは、いつから協業関係にあるのか。
原 Semtech社とは、LoRa技術の普及促進を目的に、2015年12月にパートナーシップを結んだ。さらに、ほぼ同時期に、「LoRa Alliance」にも参加している。現在、LoRa Allianceは、400社を超える企業が参加しており、非常に大きなグループとなっている。
LoRa Allianceは、どのような活動をしているのか。
原 LoRa技術に関する標準規格の策定などが主な役割だ。決まった標準規格はいずれも公開されている(オープンになっている)。そうした標準規格の1つが「LoRaWAN」であり、ネットワーク・プロトコルの標準規格である。物理層にはLoRa技術が使われており、その上位層を規定したものだ。LoRa Allianceには、400社以上の企業が参加しているが、この規格に準拠してハードウエアやソフトウエア、ミドルウエアなどを開発すれば、それぞれの互換性を確保できるようになる。
LoRaにおけるSTマイクロエレクトロニクスの具体的な活動を紹介してほしい。

図1: LoRa対応の開発キット
写真手前が「STM32 LoRa Discovery Kit」。
型名は「B-L072Z-LRWAN1」。価格は46.60米ドルである。
写真奥が「I-NUCLEO-LRWAN1」。価格は25.00米ドルである。
原 LoRa技術を使用するアプリケーションの開発に向けた開発キットを製品化している。開発キットは2種類用意した。
1つは、「STM32 LoRa Discovery Kit(型名はB-L072Z-LRWAN1)」である(図1)。これは、LoRa無線通信技術を採用したIoTノードなどの開発に向けたものだ。村田製作所の無線通信モジュールを搭載する。これには当社の超低消費電力32bitマイコン「STM32L072CZ」やSemtech社のRFトランシーバIC「SX1276」などが収められている。マイコンに搭載したADコンバータや16ビット・タイマー、UART、I2C、SPIなどの周辺機能が利用可能で、無償で提供する組み込みソフトウエア・ライブラリを活用することでアプリケーションの開発が可能だ。
もう1つは、メイン・ボードと接続して使う拡張ボード「I-NUCLEO-LRWAN1」である。当社のマイコン開発ボード「STM32 Nucleo」やArduinoボードとの接続が可能だ。当社のマイコン「STM32L052T8」や、Semtech社のRFトランシーバIC「SX1272」を内蔵した米USI社のLoRaWANモジュールを搭載する。LoRa技術の検証などに利用できる。
2種類の開発ボードの特徴は何か。
原 特徴は、それぞれの開発ボードに搭載しているマイコン、すなわちSTM32L072CZとSTM32L052T8にある。いずれも「STM32L0シリーズ」であり、消費電力が非常に低いと同時に、処理性能が高い点に大きなメリットがある(図2)。採用したプロセッサ・コアは、英ARM社の「Cortex-M0+」である。
具体的な動作時の消費電流は76μA/MHzである。これはかなり低い値だ。「Cortex-M3」コアを搭載する当社従来品「STM32L1シリーズ」と比較すると、約半分に低減することに成功した。
さらに、複数の省電力モードを用意しており、それぞれのモードでの消費電流も低く抑えた(図3)。こうした低消費性能であれば、電力メーターなどの用途でも10年程度のバッテリー駆動時間を実現することが可能になるだろう。
さらに、STM32 LoRa Discovery Kitに搭載したSTM32L072CZのフラッシュ・メモリー容量が192Kバイトと大きいことも特徴の1つに挙げられる。これだけ大きければ、ユーザー・アプリケーションを開発して格納することが可能だ。つまり、このキットだけで、LoRaを採用した実用的なIoTノードを開発できるわけだ。
700品種を超えるラインアップ
低消費電力を特徴とするマイコンを製品化している半導体メーカーは、STマイクロエレクトロニクスのほかにもある。
そうした競合他社品と比べたときのメリットは何か。
原 当社は、ARM社が提供する「Cortex-Mプロセッサ」を採用したマイコンを業界に先駆けて量産化した半導体メーカーである。その後も、Cortex-M搭載マイコンを数多く製品化している。Cortex-Mプロセッサは、「Cortex-M0」、「Cortex-M0+」、「Cortex-M3」、「Cortex-M4」、「Cortex-M7」の5種類だが、これらのプロセッサを搭載したマイコンをすべて製品化しているのは当社だけだろう。
ラインナップも豊富だ。メモリー容量の違いや、周辺機能(ペリフェラル)の違い、パッケージの違いなどで、数多くの製品を用意しており、品種数は700種類を超える。従って、ユーザーのアプリケーションに最適なマイコンが見つかるはずだ。
IoTノードは、産業機器分野などで使われる。産業機器は、製品寿命が長い。
当然ながら、それに搭載される半導体チップには、長期供給が求められる。その体制は、どのようになっているのか。
原 確かに、産業機器では、採用したデバイスのうち1つでも生産中止になってしまうと大変なことになる。特に、マイコンは機器の中枢を担うため、その影響は甚大だ。そのため、当社のマイコンは、長期供給が保証されている。毎年更新されるのだが、その年の1月1日より10年間の供給を保証するというものだ。現在2017年1月1日を起算日に10年間、つまり2026年12月31日まで製品の供給が確約されている。この長期供給保証は、STの8bit/32bitマイコン全てに適用される。
最後に、LoRa技術を採用したIoTサービスの普及状況について教えてほしい。
原 現在、世界中の通信事業者が普及に向けて取り組んでいる状況にある。用途としては、スマートメーターや、農業/酪農、自然調査などで検討が進んでいるようだ。
取り組みが特に進んでいる国や地域はどこか。
原 スマートメーターについては、フランスが先行している。一方、韓国では、大手通信事業者がすでにLoRa網を張り巡らしている。IoTセンサ・ノードよりさまざまなデータを吸い上げる用途で使うようだ。中国では、マンホールの盗難抑止にLoRa対応の無線通信モジュールを取り付けるプロジェクトが進んでいる。日本も決して遅れているわけではない。大手オペレータが、フィールド・トライアルに着手しており、その成果が待たれるところだ。
STM32 LoRa Discovery kit