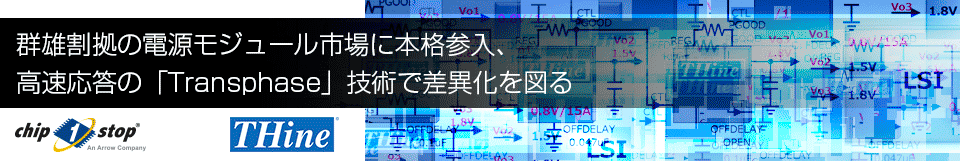水鳥貴之 氏
水鳥貴之 氏
日本における「アナログ・ベンチャーの旗手」として名高いザインエレクトロニクス。これまで「V-by-One® HS」や「V-by-One®」といった高速シリアライザ・デシリアライザ(SERDES)ICを次々と製品化し、液晶テレビやスマートフォン、OA機器、アミューズメント機器などの市場で確固たる地位を築いている。
その同社が2015年12月に「電源モジュール市場への参入」を明らかにした。2016年2月には、最初の製品「THV81800」のサンプル出荷を開始することを発表した。現在、電源モジュール市場には数多くのメーカーが参入している。国内外の電源メーカーに加えて、多くのアナログ半導体メーカーが製品を市場に投入している。非常に競争が激しい「群雄割拠」の市場と化しているわけだ。
数多くの先行メーカーに遅れて市場参入を果たしたザインエレクトロニクス。どのようなメリットを武器にして、競争を勝ち抜こうと考えているのか。そこで今回は、同社 開発部プロダクトプランニンググループでチームリーダーを務める水鳥貴之(みずとり・たかゆき)氏に、電源モジュール市場に参入した理由や、同社製品の特徴、今後の製品ロードマップなどについて聞いた
(聞き手:山下勝己=技術ジャーナリスト)。
なぜ電源モジュール市場に参入したのか。
水鳥 当社の製品は、液晶テレビなどに向けた高速インターフェースICがメインであり、これで有名になった。しかし、10年以上前から電源ICも手がけていた。DC-DCコンバータを複数チャネル集積したパワー・マネジメントIC(PMIC)である。これを液晶テレビなどの民生機器メーカーに提供していたという歴史があるからだ。
なぜ電源ICだけにとどまらず、電源モジュールも提供するようになったのか。

図1: 電源電圧の許容範囲が狭くなる
微細加工寸法が0.35μmの時代は、電源電圧が+3.3Vで、その許容範囲は±300mVだった。しかし、28nmルールでは電源電圧が+1.0Vに下がり、その許容誤差は±30mVと狭くなった。20nmルールでは、さらに許容誤差は狭くなる。
水鳥 「電源は負荷があってナンボ」である。その負荷、つまりLSIは、半導体プロセス技術の進化によって処理性能が急速に高まっており、それと同時に電源に対する要求が極めて厳しくなっているのだ。特に、電源電圧の低下が大きい。0.35μmの時代には3.3Vだったが、28nmでは1.0Vに、20nmでは0.9Vに低下した。それによって、電源電圧の許容範囲が極めて狭くなっている。3.3Vのときは±300mVを許容できたが、1.0Vでは±30mV、0.9Vでは±27mVの狭い範囲に収めなければならない(図1)。
この許容範囲を遵守することは極めて難しい。電源電圧の変動要素はたくさんある。DC-DCコンバータ回路自体の電圧設定精度に加えて、入力電圧変動(ライン・レギュレーション)や、負荷変動(ロード・レギュレーション)、温度変動、リップル電圧、負荷過渡応答などの全要素による電圧変動分を足し合わせて±30mV以内や±27mV以内に抑え込まなければならない。
ただでさえ、非常に難しい設計目標である。これをユーザーの設計にゆだねてディスクリート部品の組み合わせでクリアするのはより困難である。そこで電源モジュールの製品化に踏み切ったわけだ。
どのようなユーザー(電子機器メーカー)が電源モジュールを必要としているのか。
水鳥 電源モジュールを採用すれば、製品単価は高くなるが、設計工数や設計期間を削減できるというメリットが得られる。このメリットを評価して、ユーザーは電源モジュールを採用するわけだ。しかし、実際はその後、システムのコストを削減するために、電源モジュールの搭載をやめて、ディスクリート部品での構成に切り替えるケースが少なくない。
しかし2015年から2016年にかけて、状況が変化しつつある。出力電流が5Aを超える電源モジュールについては、ディスクリート部品に切り替えず、そのまま搭載するケースが増えている。電流が大きい電源レールの部分においては、ディスクリート部品に切り替える設計の難易度が非常に高いからだろう。
高速な負荷過渡応答を実現
電源モジュール市場にはライバル企業が少なくない。どのような特徴を打ち出して、市場を獲得する考えか。
水鳥 当社の電源モジュール「THV81800」の最大の特徴は、高速な負荷過渡応答特性が得られることだ。独自の制御方式である「Transphase」を適用することで実現した。
Transphase制御方式とは、どのようなものか。
リップル制御方式自体は、すでにさまざまな半導体メーカーがDC-DCコンバータICなどに採用している。
そうした半導体メーカーが採用している回路方式との違いは何か。
水鳥 一般にリップル制御方式には、スイッチング周波数が変動するというデメリットがある。スイッチング周波数が変動すると放射雑音(EMI)対策が難しくなってしまう。超音波診断装置などの医療機器にとっては、とても大きな問題になる。
Transphase制御方式は、このデメリットを解決している。内部の回路ブロック上で固定周波数を作成し、入出力電圧や負荷条件が変化しても、スイッチング周波数を変動させないように制御している。これが競合他社の方式との違いである。
小型ながらも高効率
THV81800の詳細を教えてほしい。
水鳥 THV81800の最大出力電流は8Aと大きい。入力電圧範囲は+7.5〜28V で、出力電圧範囲は+0.85〜4V。スイッチング周波数500kHzに設定した。変換効率は91%と高い。パッケージは、外形寸法が15mm×15mm×2.8mmのLGAである。
こうした特性の中で、競合他社品を上回っているものは何か。
水鳥 競合他社品と同レベルの小型化を実現したと同時に、競合他社品を上回る91%と高い変換効率を達成したことだ。小型化を実現できた理由は実装手法にある。DC-DCコンバータ制御IC等をダイの状態で基板に搭載しその他のディスクリート部品との理想的な配置と組み合わせでパッケージングしている。
さらに前述のように、Transphase制御方式を採用したため、負荷過渡応答特性も競合他社品を大きく上回っている。競合他社品に比べると、負荷急変時の電圧変動幅が極めて小さい。
採用したインダクタ(コイル)にはどのような特徴があるのか。
水鳥 インダクタは市販品を採用した。現在市場で入手できる製品の中で、実装高さが低いと同時に、直流抵抗(DCR)が低く、直流重畳特性に優れているものを採用した。
このほかTHV81800、どのような特徴があるのか。
水鳥 THV81800に搭載した2つの機能にも特徴がある。1つは、電源シーケンスの設定に向けて、出力電圧の立ち上がり/立ち下がりを制御する機能だ(図3)。複数のTHV81800を使用する場合、それぞれのPGOOD端子とCTL端子を接続することで、出力電圧の立ち上がり順番を設定できる。さらに、OFFDELAY端子とGND端子に接続するコンデンサの容量を調整することで、出力電圧の立ち下がり時間を設定できる。
もう1つは、出力ディスチャージ機能である(図4)。出力コンデンサの容量が大きい場合、電源モジュールがアクティブ状態からスタンバイ状態に移行した際に、出力電圧がすぐ0Vに下がらないケースが発生する。システムが誤動作する原因になりかねない。こうした問題の発生を防止するために、コンデンサの容量を強制的に放電させる出力ディスチャージ機能を用意した。
THV81800のアプリケーションとしては、どのような機器を想定しているのか。
水鳥 FPGAやVDP(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ)、DSP、カスタムSoCなどに電力を供給する用途を想定している。
第2世代品も開発中
今後の製品ロードマップについて教えてほしい。
水鳥 すでに第2世代品の開発をスタートさせている。次期電源モジュールは2017年第3四半期にサンプル出荷を始める計画である。
次期電源モジュールは第1世代品のTHV81800と比べて、電源性能を大幅に高める予定だ。最大出力電流を10A以上に引き上げると同時に、モジュールの外形寸法をより小型化する事が目標だ。スイッチング周波数は1MHz、変換効率は93%以上となる見込みだ。
制御方式には、第1世代品と同じTransphaseを採用するのか。
水鳥 基本的な原理は、第1世代品のTransphase制御方式と同じだが、第2世代品ではより進化させている。「Transphase 2」と呼んでも構わないかもしれない。
最大の改善点は第1世代品よりも出力リップル電圧を小さくしている点だ。5m〜10mVと極めて小さい値に抑えている。10mV以下に抑えられることで、この先数年以上先のプロセス技術で製造したデジタルICにも適用可能と考えている。また、入力電圧範囲は5V系, 12V系, 24V系全てをカバーしワイド入力対応とした。これによりユーザーへ部品共通化というメリットも提供できると考えている。
第2世代品で追加した機能はあるのか。
水鳥 出力電圧の立ち上がり/立ち下がり制御機能と出力ディスチャージ機能については、第1世代品に引き続き採用した。第2世代品ではこれらに加えて、外部信号で出力電圧を細かく調整する機能を載せた。これを使えば、デジタルICの動作状態に応じて出力電圧を調整することが容易に実現できる。
第2世代品のアプリケーションとしては、どのような機器を想定しているのか。
水鳥 産業機器や通信機器、医療機器、アミューズメント機器、OA機器など幅広いアプリケーションへの採用を見込んでいる。
※「Transphase」はザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
キャンペーン情報
電源モジュールTHV81800 評価ボード 無償プレゼント キャンペーン

上記でご紹介させていただいた、
ザインエレクトロニクス社製電源モジュールの評価ボードを
メーカインタビュー公開記念キャンペーンとして
抽選で10名様にプレゼントいたします!
期間:2016年12月5日~12月28日
上記のキャンペーンは終了いたしました。ご応募ありがとうございました。
ザインエレクトロニクスWebサイト上でも上記でご紹介した電源モジュールに関するコラムが閲覧可能です
「強み」を結集しPower Module市場参入を果たした、製品企画部の想い
※外部サイト(ザインエレクトロニクス社Webサイト)に遷移します。